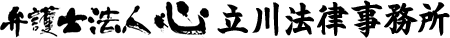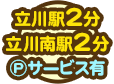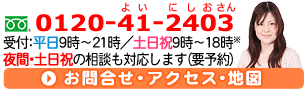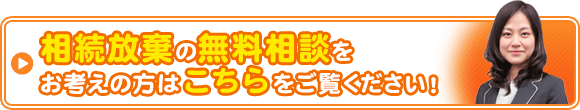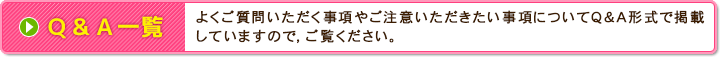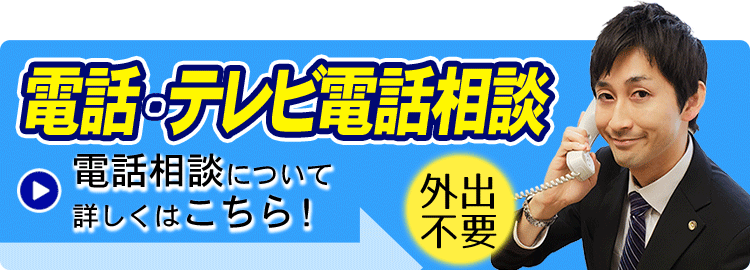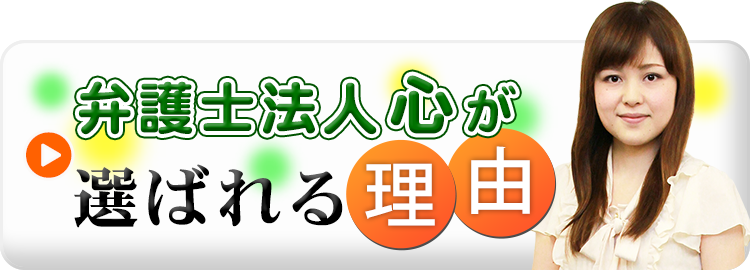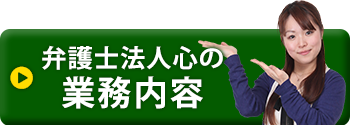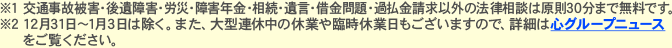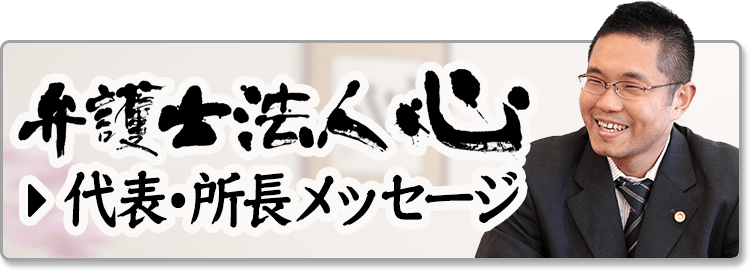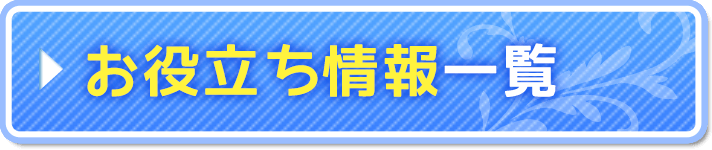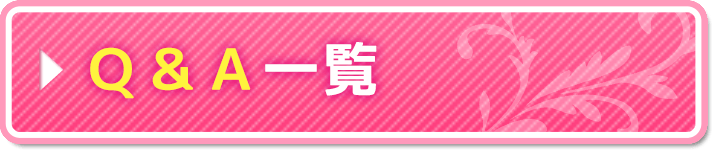相続放棄時に被相続人の最後の住所地が分からない場合の調べ方
1 被相続人の戸籍の除附票・住民票除票
被相続人の相続放棄をする際、相続放棄の申述を裁判所に受理してもらう必要がありますが、申し立てる先の裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
そのため、相続放棄をするためには、被相続人の最後の住所地が分かる資料が必要です。
被相続人の最後の住所地を示す資料として通常、必要とされるのは、被相続人の戸籍の除附票か住民票除票です。
ただし、これらの資料には保存期間が定められており、保存期間を経過していれば、入手することができません。
この保存期間は、市町村によってまちまちですし、定められている保存期間が経過していても、保存がされていることもあります。
そのため、一概に、相続が開始してから何年が経過していればこの書類を入手できないと断定することはできません。
相続放棄には期限が定められており、自らが相続人となったことを知ってから3か月以内に手続きをしないといけないとされていますので、それほど相続開始から時間が経過して相続放棄をすることはないように思われるかもしれません。
しかし、相続が開始してから長期間が経過した後に相続放棄をするということは意外と多いのです。
たとえば、相続が開始してから長期間が経過した後に、債権者を名乗る者から連絡がある場合がありますが、相続人にとって、そのような債務があることを知っていれば相続放棄をしたであろうということもあるでしょう。
被相続人が連帯保証人になっていた場合などには、被相続人に債務があることがただちに分からないことがあります。
そのようなときには、相続人に債務があることを知ったときから3か月以内に相続放棄の手続きをすれば受理が認められることがありますので、長期間が経過してから最後の住所地を示す資料が必要になることがあります。
そのときに、戸籍の除附票や住民票の除票が廃棄されていると、他の資料で被相続人の住所を疎明していかないといけません。
そのほかに戸籍の除附票や住民票の除票が利用できない場合として、被相続人が住民票上の住所に居住していないことが明らかであり、住所が消除されているという場合もあります。
そのようなときにも、他の資料を準備する必要があります。
2 死亡届の届出事項記載証明書
人が死亡したときに提出する死亡届には、亡くなった方の住所地を記載することになっています。
この死亡届が、被相続人の最後の住所地を示す資料となります。
ただ、相続人が死亡届の写しを保存し続けているということはまれでしょうし、これを入手できるということは少ないでしょう。
この証明書に利用価値がある理由は、死亡届が法務局で27年間にわたって保存されることになっていることによります。
この保存期間は、上で述べたような戸籍の除附票や住民票の除票よりも相当に長いものになっています。
そのため、上記の資料が入手できなくても、法務局で保存されている死亡届の届出事項記載証明書の発行をしてもらうことで、被相続人の最後の住所地を示す資料とすることができます。
届出事項記載証明書の発行をしてもらうためには、特別な事由が必要とされており、本来、容易に発行してもらえるものではありません。
ここでは、1の各書類が保存期間の経過によって廃棄されており、相続放棄をするためには、届出事項記載証明書の発行が不可欠という事情が必要であり、このような事情があれば特別な事由があったと認めてもらえるでしょう。
注意すべきなのは、死亡届は、提出後、ただちに法務局に移されるわけではなく、しばらくは市町村で保管されているため、その間には、市町村に対して、証明書の発行を依頼することになるということです。
ただ、相続放棄のためにこの証明書の発行を依頼するのは、相続が開始してからかなりの時間が経っているケースが多いでしょうから、通常は法務局に発行を依頼することになるでしょう。
死亡届が保管されているのは、被相続人の本籍地を管轄する法務局ですので、それを確認したうえで発行を依頼しましょう。
生活保護を受けている方の相続放棄について 遺留分についてお悩みの方へ