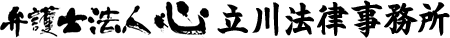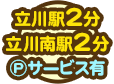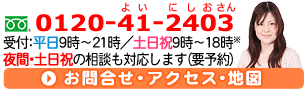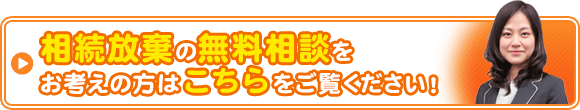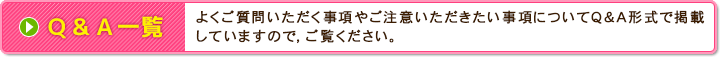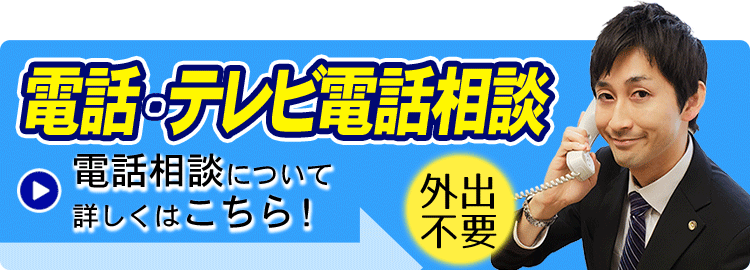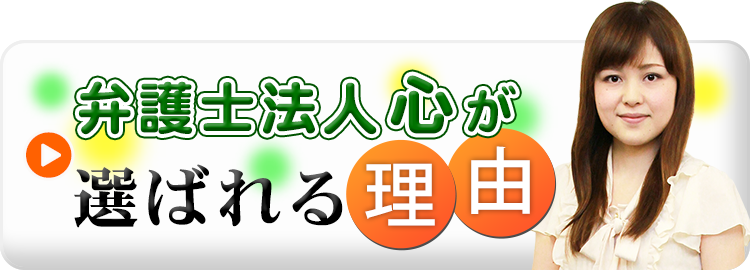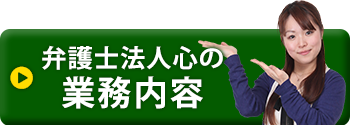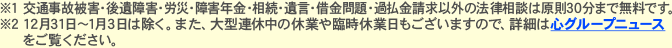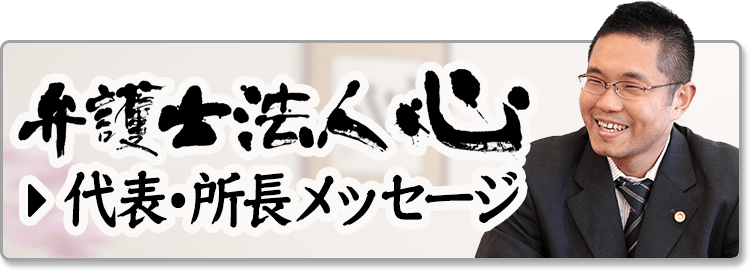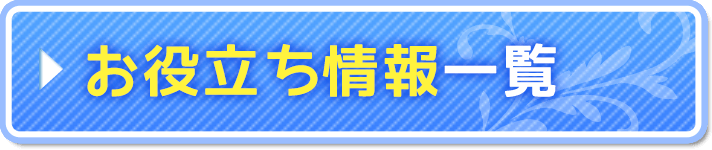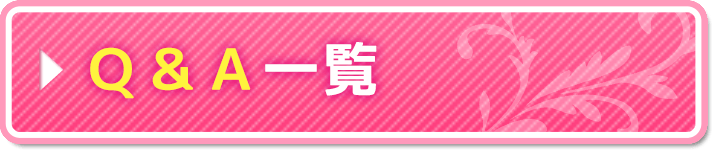生活保護を受けている方の相続放棄について
1 生活保護と相続放棄の関係について
まず、お亡くなりになられた方(被相続人)の相続人の方が生活保護を受給していても、法律上は相続放棄をすることは可能です。
民法において相続放棄が認められないケース(法定単純承認事由)がいくつか定められていますが、生活保護を受給していることは法定単純承認事由には含まれていません。
ただし、実務上は、相続放棄をしたことが、今後の生活保護の受給に影響を及ぼす可能性があります。
具体的には、被相続人の相続財産が相続債務よりも多かった場合、生活保護の受給を続けられなくなるということが考えられます。
次に、生活保護を受給されていた方がお亡くなりなられた場合も、相続人の方は相続放棄をすることが可能です。
生活保護を受給されていた方の場合、通常であれば必要最低限の財産しか保有しておらず、かつ負債を負っている可能性もあります。
経済的な観点からは、相続放棄をするべきであるといえるケースも多いです。
以下、生活保護受給者が相続放棄をする場合の生活保護への影響と、生活保護受給者の方がお亡くなりなられた場合の相続放棄について、詳しく説明します。
2 生活保護受給者が相続放棄をする場合の生活保護への影響
相続手続きの観点からは、被相続人の方がお亡くなりなられたときには、まず相続財産・相続債務の内容を調査することがとても大切です。
生活保護を受給している方においては、財産を相続した場合には、生活保護法第61条に基づいて、保護の実施機関または福祉事務所長にその旨を届け出なければなりません。
相続によって取得した財産によって生活を維持することができるようになり、「保護の実施機関」が「被保護者が保護を必要としなくなった」と判断した場合、生活保護法第26条に基づき「保護の停止又は廃止を決定」する可能性があります。
もし相続財産よりも相続債務の方が多い場合(いわゆる、債務超過に陥っている場合)、そのまま包括的に相続をしてしまうと債務の方が増えてしまい、さらに生計が悪化してしまうことになります。
そのため、被相続人が債務超過に陥っていたという場合には、相続放棄をしても生活保護の受給を継続してもよいと判断される可能性があります。
大切なことは、相続が開始したら、できるだけ早く相続財産の状況を調べ、ケースワーカー等に報告と相談をすることです。
相続放棄は、原則として相続が開始したことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。
もし相続財産・相続債務の調査に時間がかかるようであれば、予め家庭裁判所において、相続放棄の申述期限の伸長手続きをしておきましょう。
3 生活保護受給者の方がお亡くなりなられた場合の相続放棄
実務上、生活保護を受給されていた方がお亡くなりなられた際に、相続人の方が相続放棄をするというケースはよく見受けられます。
生活保護を受給されていた方がお亡くなりなられた場合、経済的な側面においては、相続放棄をした方がよいと言えます。
生活保護は、一般的には一定以上の財産を保有している方は受給することができません。
また、基本的に生活保護で受給できる金銭は、最低限の生活が維持できる程度の金額ですので、預貯金が増えるということもあまりありません。
そのため、被相続人が生活保護受給者であった場合、プラスの財産はほぼないことが多いです。
一方、病気やけがなどで働くことができなくなっていた場合、生活保護を受給する前には借金をしていたという可能性もあります。
また、被相続人に一定の財産があった場合や、被相続人の生前の事情が詳しくわかっていない場合、生活保護の不正受給をしていた可能性もゼロであるとは言い切れません。
不正受給をしていた場合、生活保護費の返還義務(債務)が生じていることもあります。
生活保護を受給されていた方がお亡くなりなった場合には、自治体に問い合わせるなどして、相続放棄をするか否かを慎重に検討する必要があります。
相続放棄をお考えの方へ 相続放棄時に被相続人の最後の住所地が分からない場合の調べ方